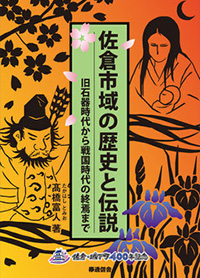- 2025.03.22
佐倉市の防災③ 応急仮設住宅
◆応急仮設住宅建設予定地の指定
大地震が発生したときに、住まいを失った人たちが最初に身を寄せるのは指定避難所です。一方、佐倉市の避難所はすべて保育・教育機関の施設が指定されているため、長く生活するには社会的・環境的に不適切です。そのため、住まいを失った被災者のために、佐倉市はできるだけ速やかに応急仮設住宅を設置し、一定期間安定的に生活していただける環境を整える必要があります。
2024年2月29日の読売新聞で紹介された、能登半島地震発生2ヶ月後の状況を再掲します。
- 発災から2ヶ月後、合計約20万人の被災市町村を調査
- 発災後2ヶ月で完成した応急仮設住宅は約300戸
- 応急仮設住宅入居申請者数は少なくとも8千戸(差し引きで7,700戸の不足)
- 応急仮設住宅の入居を待って、避難所や親せき宅に身を寄せる人の数が19,000人
佐倉市の人口は約17万人ですから、記事にある調査母数20万人は、佐倉市の人口に近似します。
上記からわかるとおり、能登半島地震で特に問題が顕在化したのが、応急仮設住宅の建設の遅れでした。対応の遅れには様々な要因がありますが、その一つにあげられるのが、平常時に行政が十分な建設予定地の指定をしていない、という点です。
先に紹介した読売新聞の記事にも、以下のような記述があります。『申請数に対し、完成数が2%の輪島市は、候補地を事前に選んでいなかった(太字は筆者)。担当者は「市有地を想定していたが場所まで決めておらず、希望数などに合わせて対応しようと思っていた」と準備不足を認める。』
発災後は、行政も罹災します。そうなると、行政機能も麻痺に近い状態になるため、事前に決められたこと以外は行動できなくなる、という趣旨の報告書が、国土交通省からも発出されています。
◆佐倉市の状況
佐倉市で、応急仮設住宅建設予定地として指定されているのは、西志津多目的広場のみであり、そこに立地できる仮設住宅の最大戸数は207戸です。
応急仮設住宅については、一般質問では3回、予算委員会の討論では1回、当会派所属議員がその重要性を訴えてきました。
本件については、3回目の質問でようやく「上座総合公園、ユーカリが丘北公園、佐倉城址公園」について、応急仮設住宅の指定に関する協議を執行部内で開始した、という答弁がありました。その間、実に1年間の歳月が流れました。
一方、地域にかたよりなく、人口割りを考慮に入れ建設予定地を設定すべきという要望については「していない」という一点張りの答弁でしたが、昨年12 月5日の三谷英継議員の質問に答えて、ようやく「特定の地域に偏ることがないようつとめる」という答弁をしました。
◆数の充足
国土交通省が公表している「応急仮設住宅建設必携 中間とりまとめ」では、応急仮設住宅立地予定地について、自治体で見積もっている大震災の全半壊戸数のうち、おおむね2から3割の応急仮設住宅の建設予定地を求めています。
先の通り、東京湾北部地震では、佐倉市は4,794棟が全半壊するとされています。
能登半島地震を前提とすると、この数も「控えめな見積」と考えますが、この数値の2割から3割といえば、およそ1千から1千500棟弱の応急仮設住宅立地予定地が必要です。
なお、全半壊する可能性のある棟数にマンションなどの集合住宅が入っている場合、被災する世帯はさらに増える可能性がありますから、上記の数字はあくまでも目安であることを申し添えます。
◆地域に偏りのない指定
地域ごとの応急仮設住宅立地予定地にこだわる理由は、全半壊した建物に住む市民が、ランダムに設定された住居にあてがわれてしまった場合、コミュニティが破壊され、最終的には孤独死などにつながるためです。
能登半島地震の報道が多数なされた通り、大災害の後、自宅から遠い地域の住宅をあてがわれ、地域コミュニティから離れた結果孤独死するご高齢者は、災害の度に問題となっています。
佐倉市は、現在65歳以上人口の比率が32%を超えています。また、65歳以上の一人暮らし高齢者世帯は、直近の国勢調査の結果である令和2年の段階ですでに8,046世帯。令和2年の佐倉市の世帯数は約78,000世帯ですから、なんと10軒に1軒以上の世帯は、65歳以上の一人暮らし世帯であり、令和6年現在はその比率はあがっているはずです。
内閣府が発表している「5.応急仮設住宅(1)総論」にも、以下のような文章が掲載されています(太字は筆者)。「入居決定に当たっては、高齢者・障害者等を優先すべきであるが、応急仮設住宅での生活の長期化も想定し、地域による互助等ができるように、高齢者・障害者等が一定の地域の応急仮設住宅に集中しないよう配慮することや、従前地区のコミュニティを維持することも必要であり、単一世帯ごとではなく、従前地区の数世帯単位での入居方法も検討することが求められる。」
人口割りを考える必要はあるものの、当会派が地域ごとに偏りのない応急仮設住宅の建設にこだわる理由は以上の通りです。佐倉市は、ようやく応急仮設住宅の具体的な検討を始めましたが、「地域に偏りのない指定」という視点は、しっかり持つ必要があります。
最近の投稿
- ふるさと広場の開発と県道64号で発生した二つの人身事故
- 佐倉ふるさと広場拡張計画に関する鯖缶さんの問への返答
- アゴラ記事目次:【連載】佐倉ふるさと広場拡張整備計画を問う
- 別添:『【連載】佐倉ふるさと広場拡張整備計画を問う』連載検証用資料
- アゴラ記事目次:佐倉市観光事業になぜマーケティングは組み込まれなかったのか
カテゴリー
- 市議会議員は何をやっているのか?
- アゴラ他メディア掲載事例
- 一般質問・討論
- 委員会等
- 議案・提出議案
- 政権公約
- 動画コンテンツ
- 政策・提言等
- 選挙
- 市政報告会・イベント
- お知らせ・日常・メモ
- 書籍・書評
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年3月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月