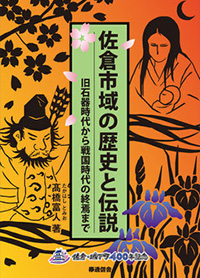- 2025.03.26
佐倉市の防災⑥ 災害協定事業者との定期的な会合・訓練
◆佐倉市の災害応援協定の状況
佐倉市は、災害応援協定を多数事業者と締結しています。
2024年12月時点で、103の協定があります。
協定先の分類で言えば、行政間の相互協定はもちろん、ライフラインの整備、生活物資の供給、医療、物流、情報伝達システム等多岐にわたります。
これらの協定は、佐倉市の担当部署の地道な努力によるものです。
大規模災害時には、行政も市民や事業者同様に被災しているため、「事前に決められたこと」以外のことはほぼ何もできない状況に陥ります。そのために、平常時に民間事業者等と協定を結び、マニュアルを確認すれば発生した事案に対応できるようにしておくことが肝要です。
◆災害協力事業者との定期的な会合・訓練
一方、「協力する側」の事業者も被災する、という前提にたてば、佐倉市がマニュアル通りに協力を要請しても、事業者側が応じることができるとは限りません。その意味で、平常時にこそ、行政と災害応援協定締結事業者との意思疎通や、発災時の訓練を定期的に実施する必要があります。
◆船橋市の事例
船橋市では、毎年一回、災害応援協定を締結している事業者のうち、特に食料や飲料水等を提供、運搬してくれる事業者との間で防災訓練を実施しています。
その訓練では、「発災→行政から協定事業者への応援要請→応援事業者側の物資確認(空箱)→搬入→運搬→指定避難所での行政の受け取り」までの業務を実施し、課題を洗い出します。指定避難所は、主に公民館を前提に、会場は毎年変更するそうです。会議参加事業者は、昨年実績ではおよそ30事業者とのことでした。
さらに、船橋市では3年から4年に一度、災害応援協定事業者との打ち合わせを実施しています。目的は「災害時における物資の供給、輸送及び集積に関する協5定を締結している事業者と、平時から定期的に協定内容の確認及び情報交換等を行うことで、有事の際の対応を円滑に行える体制を整えること」であり、特に「協定内容の確認」と「情報交換」を担当者同士が会って話し合いをしておく、ということが重要と考えているそうです。実際、話し合いの中で、これまで見えていなかった運搬ルートに関する課題などが、会合の都度見えてくるとのことでした。
確かに、「いざ発災」となった後、平常時には災害に関する意思疎通をしていない事業者にマニュアル通り依頼をかけても、事業者側が対応できる可能性は低いと考えられます。そこで、当会派の所属議員が、2020年の12月3日の一般質問で「協定事業者との連絡体制の構築について」を質しましたが、佐倉市は「やるつもりはない」という答弁でした。
これも、目標値を設定し、早急に取り組まなければならない事業と考えます。
最近の投稿
- 髙橋とみお:里山自然公園に関する一般質問一覧
- 【2026年2月15日時点】佐倉里山自然公園・民有地買収をめぐって
- 佐倉ふるさと広場拡張計画を検証する:ドッグランとBBQ③
- 佐倉ふるさと広場拡張計画を検証する:ドッグランとBBQ②
- 佐倉ふるさと広場拡張計画を検証する:ドッグランとBBQ①
カテゴリー
- 市議会議員は何をやっているのか?
- アゴラ他メディア掲載事例
- 一般質問・討論
- 委員会等
- 議案・提出議案
- 政権公約
- 動画コンテンツ
- 政策・提言等
- 選挙
- 市政報告会・イベント
- お知らせ・日常・メモ
- 書籍・書評
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年8月
- 2025年6月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年3月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月